「ふるさと納税」という言葉は聞いたことがあるけれど、「なんだか難しそう…」「自分には関係ないかな」そう思っていませんか?

ふるさと納税って難しい?
実はふるさと納税は、たった2,000円の自己負担でお米やお肉、フルーツなどの豪華な返礼品がもらえる、とってもお得な制度なんです。
この記事では、ふるさと納税の仕組みからメリット、そして具体的なやり方まで、初心者の方向けにわかりやすく解説していきます。
ふるさと納税とは?


ふるさと納税は、「寄付」という名前の、税金の前払い制度です。
自分の好きな自治体を選んで寄付をすると、寄付した金額に応じて翌年の住民税や所得税が控除される仕組みです。
実質的に、税金を自分が応援したい自治体に移し、そのお礼として特産品がもらえる、というイメージですね。
どんなメリットがあるの?
ふるさと納税には、主に3つのメリットがあります。
1.お礼の品(返礼品)がもらえる
お米、お肉、海産物、フルーツ、旅行券など、全国各地の魅力的な特産品から好きなものを選べます。日用品を選ぶと生活費が安くなったります。
2.税金が控除される
寄付した金額のうち、自己負担2,000円を除いた全額が、翌年の税金から控除されます。
3.全国の自治体を応援できる
被災地の支援や環境保全など、自分が応援したい活動をしている自治体を選んで寄付することで、社会貢献にも繋がります。
どうやってやるの?
ふるさと納税は、意外とカンタンに始められます。基本的な流れは以下の通りです。
1.ふるさと納税サイトで商品を選ぶ
「楽天ふるさと納税」がおすすめです。サイト内には返礼品が豊富に掲載されており、普通のネットショッピングと同じ感覚で選ぶことができます。
2.決済方法について
ふるさと納税は、クレジットカードやコンビニ払いなど、様々な方法で寄付できます。
楽天ふるさと納税の場合
クレジットカード(Visa、Mastercardなど)
楽天ペイ
銀行振込
コンビニ払い
3.翌年の税金から控除される
寄付をした後、税金の控除手続きをすることで、翌年の住民税などが安くなります。手続きには「ワンストップ特例制度」か「確定申告」のどちらかを選びます。
初心者がつまずきやすい注意点
ここだけ押さえておけば大丈夫!というポイントをまとめました。
1. 自己負担額は2,000円
寄付金額がいくらであっても、自己負担額は一律2,000円です。これは、寄付した金額のうち、2,000円を除いた全額が翌年の税金から控除される(税金が前払いされる)仕組みのためです。たとえば10,000円寄付した場合、8,000円分が税金から差し引かれ、実質的な負担は2,000円となります。
2. 控除上限額を超えないように
年収や家族構成によって、控除される金額には上限があります。この上限を超えて寄付をすると、2,000円以上の自己負担が発生してしまい、ただの寄付になってしまうので注意が必要です。事前にシミュレーションサイトでご自身の控除上限額を確認しておきましょう。
3. ワンストップ特例は5自治体まで
会社員など確定申告をする必要がない人向けの「ワンストップ特例制度」を利用すれば、書類を郵送するだけで手続きが完了します。ただし、この制度が使えるのは寄付した自治体が5つまでです。6つ以上の自治体に寄付した場合は確定申告が必要になります。
おすすめの返礼品を紹介
毎年寄付している餃子🥟めちゃくちゃおいしくて何個でも食べれちゃう🤭
ずわいがにも毎年定番🤭🦀好きにはたまらない😮
ティッシュは必需品☺絶対使うものだから生活費が安くなる
控除上限額をシミュレーションしよう!
「自分の年収だと、いくらまで寄付できるの?」と疑問に思いますよね。 ふるさと納税で最も重要なのが、この「控除上限額」です。この金額を事前に知っておくことで、自己負担2,000円を超えて寄付しすぎるのを防ぐことができます。
上限額は、年収や家族構成によって異なります。
【シミュレーションサイトの活用】 複雑な計算は不要です!多くのふるさと納税サイトには、無料で使えるシミュレーションツールが用意されています。
楽天ふるさと納税の場合
- 楽天ふるさと納税サイトを開く。
- サイト上部にある「かんたんシミュレーター」をクリック。
- 源泉徴収票を見ながら、「年収」「家族構成」などの情報を入力。
- 「計算する」ボタンをクリックすると、あなたの控除上限額が表示されます。
【シミュレーションのポイント】
- 正確な年収を入力する
- 源泉徴収票に記載されている「支払金額」や、お給料明細の「総支給額」が目安になります。
- 副業収入がある場合は、それも含めた総所得で計算しましょう。
- 扶養家族の有無もチェック
- 配偶者や子どもの有無、扶養している人数によっても上限額は変わります。
- 配偶者や子どもの有無、扶養している人数によっても上限額は変わります。
- あくまで「目安」として利用する
- 計算サイトは、あくまでシミュレーションです。最終的な上限額は、所得控除の状況などによって変わることがあるため、余裕を持った金額で寄付するのがおすすめです。
シミュレーションで自分の上限額がわかったら、あとはその範囲内で安心して返礼品を選べます。
まとめ
ふるさと納税は、「自己負担2,000円でお礼の品がもらえる制度」です。
「難しそう…」と思っていた方も、この記事で仕組みややり方がわかっていただけたのではないでしょうか。
まずはご自身の「控除上限額」を確認して、ぜひふるさと納税を始めてみてくださいね!
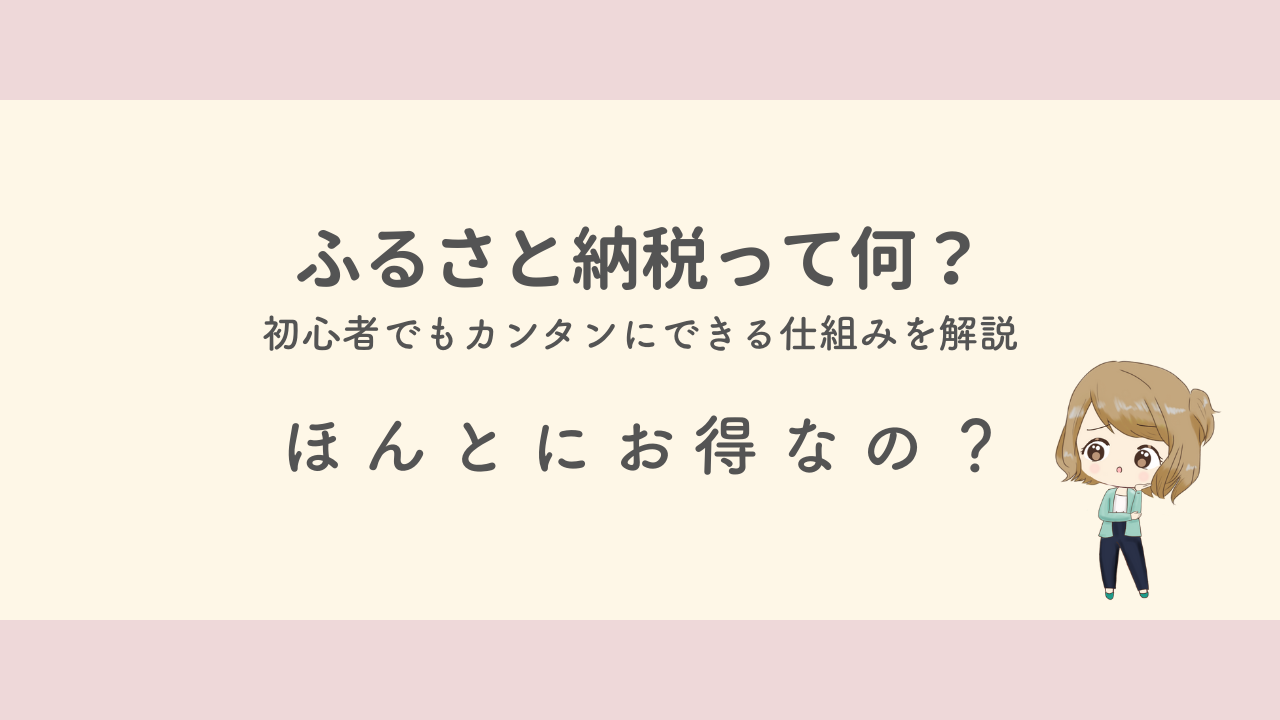
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2e015bf5.611ef85f.2e015bf6.031d5486/?me_id=1342148&item_id=10001543&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff192023-fujiyoshida%2Fcabinet%2F08816496%2F08816497%2Ff173-001-002-s-r.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/22511324.fa651abc.22511325.089acf6f/?me_id=1365796&item_id=10000642&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff042056-kesennuma%2Fcabinet%2F2025%2F20565778.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2125477a.2768b408.2125477b.0617f08c/?me_id=1377752&item_id=10000331&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff092088-oyama%2Fcabinet%2F1256759lp_01_r_re2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント